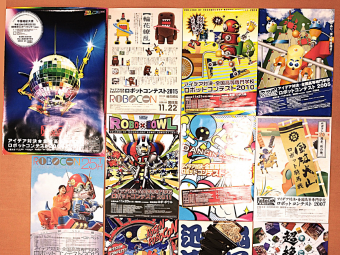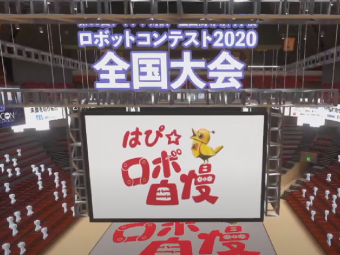高専トピックス
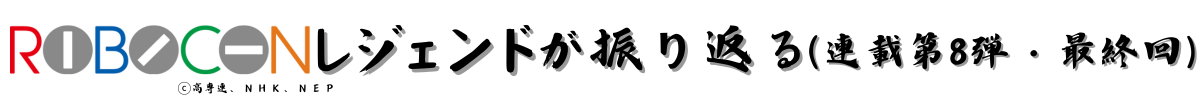
存続の危機を乗り越えた高専ロボコンと技術者教育の側面
徳山高専 准教授 藤本 浩 先生

徳山高専のこれまで高専ロボコンに出場した歴代のロボットたち。
1988年に始まった高専ロボコンで、藤本先生は初期の頃から学生の指導に携わり、そのロボットたちは今も大切に保存されています。
これまで7回執筆させて頂いた通称 ”高専ロボコン” はその名称を「アイデア対決独創コンテスト」→「アイデア対決ロボットコンテスト」→「NHKアイデア対決ロボットコンテスト(高専部門)」→「アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト」と時代の流れと共にその名称を変えてきました。
しかし、何れの時代においても ”アイデア対決” の冠を外すことはありませんでした。単に試合の勝ち負けを競う大会ではなく、若い選手達が夢やアイデアを競うことを通じて発想力豊かな技術者を育てることを最大にして最終の目的としていました。高専ロボコンは、ロボコン大賞を最高位の賞として位置づけて、他のロボット競技大会とは一線を画す形で1988年からの開催から長期に渡り、大会設立の立役者であり、2025年1月12日に惜しまれながらご逝去された東工大名誉教授の森正弘先生の熱い思いを現在に伝えてきました。
大会を運営するに当たってはNHK関連グループ(以下、NHKと記す)は元より、協賛企業からも資金面で多大な援助を得ています。大会初期の1990年から2001年までは当時の国内パソコンのシェア率が70%とも80%ともいわれたNEC(日本電気株式会社)が特別協賛企業として巨額の運営資金を提供していたこともあって、地方大会から全国大会を通じてその運営の殆どをNHKが担当していました。
地方大会の会場は特別な理由がない限り高専の体育館を利用していましたが、徐々に高専ロボコンの知名度が上がってくると観戦希望の人数が増えてきたことと、一般には高専の知名度が低かったこともあって、高専側としては大会が絶好のアピールチャンスであるとの思惑から地方の大型多目的体育施設などで大会を開催するようになりました。

1999年 第12回高専ロボコン「ジャンプ・トゥー・ザ・フューチャー」で配布されたトレーナー。
当時は毎年、選手と指導教員にトレーナーが配布されていました。オリジナルキャラクターの「アイデアの卵」が描かれています。
当時の潤沢な大会予算の片鱗を伺わせるものが手元に残っていましたので紹介します。まず、毎年デザインの異なるオリジナルキャラクターをプリントしたトレーナです。選手と指導教員に地方大会と全国大会でそれぞれ配布されていました。
さらに、毎年このオリジナルキャラクターをアレンジした大型の多色刷りポスターがありました。このオリジナルキャラクターを我々は「アイデアの卵」と呼んでいましたが、伝え聞いた話によると、このキャラクターの著作権はNHKのものではないということで、NECが特別協賛を脱退すると共にトレーナーの配布はなくなり、ポスターのデザインからも「アイデアの卵」がなくなりました。
残念ながら手元にはこのキャラクターを使ったポスターは2000年大会のものが1枚、トレーナーは2着しか残っていませんでした。高専ロボコンのキャラクターとして一時期「ロボドーモ君」もありましたが、やはり私はこの卵のキャラクターが好きでしたので、なくなったのは今でも残念でなりません。余談ですが、このキャラクターを模倣したロボットで全国大会に出場したことがあって一時物議をかもしましたが、結局、著作権先からの許可が出たらしく放送映像にモザイクが入ることはありませんでした。
その他にも地方大会に新人タレントの起用がありました。私達の中国地方大会には覚えているところでは女優の「仲間由紀恵」さんや地元出身タレントの「松村邦洋」さんによる大会中でのリポートもありました。
その後、NECが特別協賛を脱退したことによる運営資金面の減少から、高専ロボコン存続の危機が訪れ、このことについて高専とNHKで協議が持たれました。
このとき大会の存続について技術者教育の視点からの話としてあまり聞こえてこなかったのは残念でしたが、高専側からはNHKの放送を通じて高専の情報を大衆メディアに載せることのメリットを重要視して、これまで以上に資金面と大会運営に全高専を挙げて協力することとして高専ロボコンが存続することになりました。現在は特別協賛の「本田技研工業株式会社」をはじめ、協賛7社、特別協力3社、協力3社1機構の支援を得て大会が継続されています。
さて、大会の存続協議の際に「技術者教育の視点からの話としてあまり聞こえてこなかった。」と述べましたが、ある意味仕方のないことだと思っています。
その理由は、各高専のロボコンへの取り組み姿勢にもよりますが、高専ロボコンの指導にあたってはその多くはロボット作りに必要なスキルを持ち合わせている特定の教員が毎年担当するケースが少なくないからです。その結果、指導の詳細とその教育効果については各高専で共有されることは殆どありません。必然的に高専ロボコンによる教育的な優位性がどの程度あるのかは大会の結果でしか評価されないことになります。このようなことから高専ロボコンの教育的な優位性について問われた場合には、私見とはなりますが、高専ロボコンを長年指導してきた経験と他の高等教育機関に先行して創造教育を体系的にカリキュラムに取り入れ実践してきた経験から、ロボコンを経験した学生とそうでない学生とを比較した場合、取り分け発想力とアイデア具現化のセンス、課題解決能力の向上には歴然とした差が生じるといえます。
特にロボットの設計を主として担当した学生は、夏休みを通して最低でも毎日6時間以上は課題解決のためのアイデアや機構のイメージを考え、それを形にする取り組みを自主的におこなっていますので、このような差が出るのは必然のことといえます。こういった教育的効果を定量的に比較することは難しいのですが、参考のため私の元に現存する過去のロボット達(※)をまとめて掲載していますので、これをご覧になった上でこの点を推し量って頂ければ幸いです。
※過去のロボット達については、徳山高専HP 「高専ロボコンの歴史」ページ をご覧ください。
ともあれ、技術者や研究者はストイックなまでにもの作りや開発に没頭する傾向があるといわれますが、高専の学生も例外ではありません。その反面、大衆コミュニケーションを苦手としている者も多くいます。高専ロボコンではチームを組んで一つの競技ロボットを完成させる作業なので、否応なしにチーム内でのコミュニケーションが必要となることで、その能力が鍛えられます。更にはメディア取材におけるコメントを求められることもあって、本来自分の考えを伝えることを苦手としていた学生がこれらの経験を経てチームのリーダーとして成長することも珍しくありません。
コンテストが始まった1988年の「乾電池カースピードレース」の放送は、学生達の発想の豊かさ、その発想に焦点を当てた競技型式の斬新な番組として視聴者を随分魅了したことと思います。そのためNHKも継続番組として成立させたのではないかと察します。私もこの放送に魅了された一人でしたので、それから2年後にロボコンに関わるようになりました。当時目新しかったロボコンも現在では小学生から大学生まで様々な分野で参加できるロボコン型式の競技が数多く開催されるようになりました。

2013年 第26回高専ロボコン「Shall We Jump?」に出場した奈良高専のロボット「じゃんぺん」。
この大会では徳山高専が優勝しましたが、準優勝となった奈良高専の「じゃんぺん」は、後に “Most skips by a robot in one minute”(1分間に最も多くロボットが縄跳びを跳んだ回数) でギネス世界記録を樹立しました。
ロボコンの創世記には将来ロボットが今ほど活躍する時代になるとは考えていませんでしたので、選手達も単に技術を使った趣味的な範疇で取り組んでいたと思います。しかし、30年後の現代においては少子高齢化、働き方改革、災害救助、海洋開発、生産コスト削減などで、その一翼を担う救世主として様々なロボットが必要となっています。当時は職業として考えられなかったロボット作りの知識がそのまま職業に繋がる時代となったわけです。
19年前に選手として活躍した学生の一人は協賛企業の一つに研究職として入社し、上司も褒め称える会社の柱となっています。そしてこの会社のエンジニアの半分近くが大学経由を含め高専卒だということです。昨年の大会決勝戦で惜しくも敗退した熊本高専の女性選手が表彰式の場面で感動的なコメントを残しています。「メンバー達とロボコンをやっている空間が宇宙一楽しかった。」このような空間を経験できる若者が今どれ程いるでしょうか。この感動と今の思いを忘れることなく19年前の選手と同じように社会で活躍できる思いやりのあるエンジニアとして育っていくことでしょう。

大会に参加した学生のコメントには、技術やアイデアに関する感想よりも、仲間や先輩後輩と昼夜を問わず苦労を分かち合った感動的なコメントが多く聞かれます。
最後となりますが、一時期は世界第2位のGDPを誇っていた日本経済を背景に、高専ロボコンもこの時期、年を追う毎に大変な盛り上がりを見せていました。しかし、1997年に消費税が5%になって以降の日本経済は衰退の一途をたどり2002年からのNECの特別協賛脱退を契機に一時は高専ロボコン消滅の危機に瀕しました。その後も日本経済の停滞が叫ばれる中で、復活に向けての苦悩が続いています。
一方で、世界に目を向ければ日本以外の各国は右肩上がりの経済成長を果たし、ITや産業技術面での発展は著しく、身近なものとして3Dプリンターやドローン技術など、日本は高い技術的ポテンシャルを秘めているにも関わらず他国に後れを取っているのが現状です。高専においては高専機構からの分配運営経費は減り続けています。入学は難関であっても教育設備の充実ぶりが高専を受験する大きな理由にもなっていましたが、遂にパソコン設備すら賄えず、受益者負担の名の下に個人調達のパソコンに切り換えざるを得ない窮状となっています。世界最大の対外純資産国である日本が将来への投資として教育への財政出動が待ったなしの課題であると私は考えます。

藤本 浩
徳山工業高等専門学校 機械電気工学科 嘱託准教授
創造・特許教育を担当、二重螺旋ポンプ、電動車椅子用着脱可能な安全停止装置、乳幼児うつぶせ寝検出装置など数々の開発及び応用と、高専ロボコンには1991年開催の第四回大会から指導者として参加し、全国大会優勝、準優勝、ロボコン大賞、技術賞、アイデア賞等幾多の実績を有する。
『SolidWorksによる3次元CAD -Modeling・Drawing・Robocon』(共著)
(掲載開始日:2025年3月24日)